| | | | | |
| だまって、コイツを聴いてくれ!(第6回) | |
ボズ・スキャッグス/シルク・ディグリーズ
BOZ SCAGGS /SILK DEGREES
| |
| | | | | |
CD/CBS SONY CRCS 6021 1976年
1.WHAT CAN I SAY
2.GEORGIA
3.JUMP STREET
4.WHAT DO YOU WHAT THE GIRL TO DO
5.HARBOR LIGHTS
6.LOWDOWN
7.IT'S OVER
8.LOVE ME TOMORROW
9.LIDO SHUFFLE
10.WE'RE ALL ALONE
| |
| | |
東京のダウンタウンは、いつの時代でも不良少年達のメッカであった。
1970年代の中頃といえば、今では「ビーバップ・ハイスクール」ぐらいでしか拝めなくなった、軍鶏のトサカのように見事なリーゼントが、街中を闊歩していたものである。 そんな時代のこの街に、ひとり長髪の不良を目指している少年がいた。
少年の御本尊は、英吉利産の転石楽団(注1)。中学2年の時に、歯抜けた魔女に一発かまされて以来、少年は髪をおろし、バイクの代わりにギターを手にするようになったのである。
そんな少年にとって、この頃にわかに流行り始めたAOR(注2)は、まさに親の仇のような存在であった。「軟弱な音のロックなんか、やるんじゃねーよ!」
しかし、自称硬派少年の岩のような信念も、女という魔物の前では無力であった。少年の惚れた女の愛聴盤がなんと、このAORの代表選手ボズ・スキャッグスの『シルク・ディグリーズ』だったのだ。
「私、ボズ・スキャッグスが好きなんだけど、○○クンは?」
「えっ…?きっ、聴いたっことないんだけど…。」
「そう、じゃあ、レコード貸してあげるネ!」
「あっ…?う、うん…。」
女のマタのチカラと書いて、努力と読む。げに、女のマタの威力はかくのごとし(?)硬派日本男児の岩のごとき信念は、一瞬にしてサラサラの砂と化してしまったのである。
少年は、「誰にも見つからないよーに」と、彼女の部屋のかぐわしき移り香も悩ましいLPレコードを小脇に抱え、一目散に家路をたどったのであった。そしてなぜか、誰もいない家の中であるにもかかわらず、ヘッドフォンをかまして『シルク・ディグリーズ』を聴いたのである。ああ、小心モノよ。
| |
 | |
↑「♪く~も~り、ガラスのむこうは~♪」
の寺尾聡ではない。
ボズ・スキャッグス兄いである。
| |
| | |
| | | | | |
数秒後、ヘッドフォンの中に未知の世界が広がった。
おそるべし、m7(マイナーセブンズ)コードの効用(注3)。ここに、9thのテンションがかかると、なおよろし。レズリースピーカーをかましたエレピで弾くと、即昇天間違いなし!の極楽アイテムである。暗くもなく明るくもない和音の響きは、少年が知っていたメジャーかマイナーかの、黒か白か、丁か半か…、斬ったハッタの世界とはまったく別モノであった。この中途半端でフワフワした感じは、クセになりそう。
そして、ピシーッピシーッと、下半身を直撃する鞭の音、じゃなかった、シャープなハイハット・ワーク。ほどよく張った、スネアの響き。ドラム好きギター少年のツボを押さえまくる、ジェフ・ポーカロのドラミングが、少年の快感を増幅させたのである。ああ、ジェフ、10数年後に、農薬アレルギーなどで神のもとへ召されることになるとは、おシャカ様でもご存じなかったことだろう。
さて、当のボズのヴォーカルはどうだったか、というと。これは、あせらず力まず、テキトーに力の抜けた、安全運転の見本のようであった。少年には、この安全運転ぶりが、クールでお洒落で、都会っぽいセンスと感じられたのだ。この人が、スティーヴ・ミラー・バンドなどという、マニアックな暴走集団の構成員だったとはとうてい信じられない。分家して、垢抜けたのだろうか。そういえば、世界でもっとも有名な便器であるTOTOは、『シルク・ディグリーズ』からの分家である。
さらに、当時お茶の間のアイドルになりつつあった、竹中茶々丸先輩(注4)のファースト・アルバムの元ネタが、実はこの『シルク・ディグリーズ』と知り、少年はふたたびショックを受けるのであった。あのフツーのロックでは味わえない感覚は、そうかここから来ていたのか。たしかに「シャイニン・ユー、シャイニン・デイ」は、「ロウダウン」であり「ホワット・キャン・アイ・セイ」だ。竹中茶々丸先輩は、m7(マイナーセブンズ)コードや16ビートのリズム感覚を、我が国の芸能界に持ち込んだパイオニアである。そのルーツが、『シルク・ディグリーズ』とは恐れ入った。
その後少年は、8ビートの曲でも倍の16ビート感覚でリズムをとるようになり、カッティングの合間に「シャカポーンッ!」という合いの手を頻発するようになり、キーボードプレイヤーがオツムをひねるようなテンションコードを平然と使うようになり、さらには自分の結婚式のBGMに「ウィー・アー・オール・アローン」を使うに至った。あの時、彼女に『シルク・ディグリーズ』を借りなかったら、あのままキース親父のクローンになっていたことは疑いなく、必然的にジェフ・ベック師匠の『ブロー・バイ・ブロー』や『ワイアード』に対する理解が遅れたことだろう。
とにかく、余計な先入観を捨て去り、ボズ・スキャッグスの華麗な世界に身を任せるとよい。きっと、今まで体験したことのない快感に、出会えるはずだ。これで果たして名盤紹介になっているのか、文中の少年とは筆者のことなのか、はたして少年と彼女は結ばれたのか、などという素朴な疑問はさておき、 黙ってコイツを聴いてくれぃ!
| |
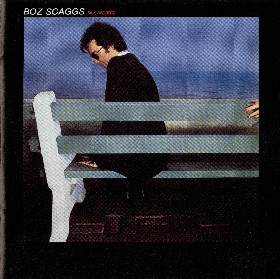 | |
↑いかにも、“アメリカン・アート”
といった雰囲気のジャケットだ。
こういう色使いは、我々にできそうにない。
右端の女性の、マニキュアがアクセント。 | | |
| | |
| | | |
(注1) 英吉利産の転石楽団
顔の筋肉の切れかかった大口野郎と全身の血液を交換してしまったチンパンジー野郎を中心とした、世界最高のロック・バンド。ライバルであるカブトムシ野郎どもがリタイアして、四半世紀以上が経過しているのに、いっこうに引退する気配がない、まことに天晴れな野郎どもである。
(注2) AOR
死語。Adult・Oriented・Rockの略。Adult といっても、18禁のことではない。大人 向けのロックという意味で、1970年代後半にさかんに使われた。ボズ・スキャッグスやスティーリー・ダンが代表選手である。リッチー・ブラックモアは当時のインタビューで、「アメリカンナイズされた、俗悪で堕落した音楽」と非難した。
(注3) m7(マイナーセブンズ)
主音、短3度、5度、短7度で構成される和音。どういう音なのか知りたければ、弾いてみろ。どうも、この少年は、ピーター・フランプトンからmaj7(メイジャーセブンズ)を、ボズ・スキャッグスからm7(マイナーセブンズ)の蜜の味を教わったらしい。
(注4)竹中茶々丸先輩
本名、CHAR。少年の中学時代の悪友で、大田区から転校してきた、Hの兄貴の高校(都立大崎高校)の先輩。ちなみに、Hの兄貴もプロミュージシャンで、山の名前を芸名に使ったアイドルのバックバンドに在籍していた。少年の60~70年代ネタの仕入先は、この兄弟である。茶々丸先輩は、「気絶するほど悩ましい」でハジケ、その後“地味変”になったらしい。
| |
| | | |
 | |
| | | | | | | | | | |