| | | | | |
| シリーズ:20世紀を生きぬいた巨人達・第3回 | |
| マイルスは、「So what?」と言い続けた | |
1、「オマエは今日まで、オレのために服を創ってきたのか?」
マイルス・ディヴィスが、1986年に来日した時のことだ。
「なにか、オモシロイ服はないか?」と言うマイルスに、プレス関係者が一人のデザイナーを紹介した。その名は、佐藤孝信。マイルスは早速、佐藤氏のブランド、アーストンボラージュ(arrston volaju)を訪ねた。
商用で外出していた佐藤氏は、オフィスに入れた電話でマイルスの来訪を知った。「早く、戻ってください。」と焦るスタッフ。しかし、佐藤氏はこの時、まだマイルスをそれほど詳しくは知らなかったという。「とにかく、戻ろう。」ということになって、急いでオフィスに戻ってみると…。
ショールームの奥の暗がりに、マイルス・ディヴィスがいた。
そして、「How are you?」と声をかけた佐藤氏のもとへズカズカとやってきて、こう言ったそうだ。
「オマエは今日まで、オレのために服を創ってきたのか?」
「…!」
OH、なんてこった!この、ゴーマンさはどうだ?まるで、万物が自分を中心に回っているかのごときセリフを、こんなにあっさりと言ってのけるとは。
しかし、そんな常識的な反応を示したら、きっといつもの口癖で一蹴されたことだろう。
「So what?」
「それがどうした?」、と…。
一撃で佐藤氏をKOしたマイルスは、どこ吹く風といった様子で「ここは宝島か」などとうそぶいている。そして、おもむろに、服を選び始めた。佐藤氏はここで、このゴーマンなオッサンが只者ではないことを、イヤというほど思い知らされることになるのだ。
「これほど、僕の服が似合う人がいるだろうか?」
佐藤氏は、マイルスのセンスに舌を巻いたという。
アーストンボラージュの服は自己主張が強く、普通の人ではその個性に圧倒されてしまいがちだ。しかし、マイルスだけは違ったようである。服の個性に負けないだけの強力なオーラを、マイルス自身が放っているからだ。服に負けるような、ヤワなオッサンではない。
しかも、
マイルスは気に入ると、サイズも何も関係なしに着てしまうのだ。コートの裾を引きずろうが、ズボンが大きかろうが、そんなことには一切お構いなし。そして、普通なら似合うハズのない格好でも、マイルスがするとサマになってしまう。佐藤氏は、周囲のものすべてを自分の中に取り込んでしまう、マイルスの類い稀なる才能に驚かされたという。
翌年、佐藤氏はマイルスのステージ衣装をデザインすることになる。そしてマイルスはモデルとして、佐藤氏のファッション・ショーにまで出演してしまう。佐藤氏は、ニューヨークを訪ねるたびに、たくさんの服をお土産として持参するようになり、お土産を貰ったマイルスは、自室で一晩中ファッション・ショーに興じるのであった。マイルス・ディヴィスは、その晩年に最も信頼したと言われているパートナーと、このようにして出会った。
マイルスのファッション・センスは、そのまま彼の音楽活動にも当てはまるといえる。
“周囲のものすべてを自分の中に取り込んでしまう、類い稀なる才能”
そう、万物は、このゴーマンなオッサンを中心に回っていたのである。
| | | |
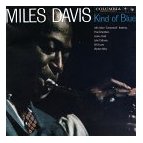 | |
↑マイルスを聴いたことのない人には、まずこれをおススメする。
『カインド・オブ・ブルー』(1959年)
| |
| | | 2、「オレのバックで、ピアノを弾くな!」
1954年のクリスマス・イブのことだ。
マイルス・ディヴィスは、ジャズ界の先輩である大物ピアニスト、セロニアス・モンクとレコーディング・セッションをすることになった。
セロニアス・モンクは1920年生まれ。「ミントンズ・プレイハウス」のハウス・ピアニストとして活躍し、“バップの高僧”(モンクは、僧侶を意味する)と呼ばれた。ハーレム・ピアノを継承しながら独自のスタイルを築き上げ、1940年代にはすでに「ラウンド・ミッドナイト」をはじめとする、代表作の大半を完成させていた。
マイルスは1926年生まれ。モンクより6才年下である。
この、年齢もキャリアも上の先輩に向かって、マイルスはこう言ったそうだ。
「邪魔だから、オレのソロのバックで、ピアノを弾くな!」
「…!」
マイルスは、まだオッサンにならないうちからゴーマンだったのか?そんなに若い頃から、万物はアンタを中心に回っていたのか?
しかし、この感情的な対立が起爆剤となり、2人は緊迫感あふれる演奏を残した。(『マイルス・ディヴィス&ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ』、『バグズ・グルーヴ』)そして、翌年の「第2回ニューポート・ジャズ祭」で、この2人は再び共演しているのだ。
“天才の心、天才のみ知る”といったところだろうか。
またもや、マイルスに一蹴されそうである。
「So what?」
そんなゴーマンなオッサンは、才能あるスタッフを大事にした。
1950年代の後半、「あのヘタクソなテナーを、クビにしろ。」などと非難されながらもジョン・コルトレーンを使い続け、ついにその才能を開花させたことなどは最たる例といえる。マイルスは、他人の能力を見抜くことができる、確かな“眼”を持っていたのである。1960年にマイルスから独立したジョン・コルトレーンは、その後67年に40歳の若さで亡くなるまで精力的に活動を続け、後世に“伝説”として語り継がれるべきミュージシャンになった。しかし、マイルスがいなかったら、はたして今日のような評価を得ることができたかどうか…。
独立したコルトレーンが絶頂期を迎えていたのとほぼ同時期、マイルス・ディヴィスのスタッフもまた最強の布陣を誇っていた。それは、1964年から68年にかけてのこと。俗に“黄金のクィンテット”などと呼ばれている、マイルス・ディヴィス(トランペット)以下、ウェイン・ショーター(テナー・サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、トニー・ウィリアムス(ドラムス)の5人。いずれも、後にジャズ界の重鎮となる面々である。
このメンバーで録音した、『マイ・ファニー・バレンタイン』、『フォア&モア』、『E・S・P』、『ソーサラー』、『ネフェルティティ』は、マイルスの代表作であると同時に、ジャズを代表する名盤として評価されている。そして、その集大成ともいえる、シカゴのライブハウス「プラグドニッケル」におけるライブ(『ライブ・アット・プラグドニッケル』)は、“4ビート・ジャズの奇跡”とまで言われている。
しかし、マイルスはこの“黄金のクィンテット”を、自ら解体してしまうのだ。
1968年暮れに、まずロン・カーターにクビを宣告する。才能あるスタッフを解雇した理由は、ロンが「エレクトリック・ベースを弾くことを拒絶したから」である。
マイルスは、1968年5月発表の『マイルス・イン・ザ・スカイ』で初めて、ハービー・ハンコックにエレクトリック・ピアノを弾かせた。そして、ジョージ・ベンスンが、エレクトリック・ギターで参加したナンバーも収録されている。
同年9月発表の『キリマンジャロの娘』では、チック・コリアがエレクトリック・ピアノで参加、デイヴ・ホランドがエレクトリック・ベースを弾いている。
この時期のマイルスの興味の中心は、ジェイムズ・ブラウンやスライ&ファミリー・ストーンといったファンク系のミュージシャン。そして、ジミ・ヘンドリックス。マイルスは、電気楽器を使用する必然性を痛感していた。
マイルスは、自身のトランペットにピックアップを装着し、アンプで音を増幅させた。そして、エレクトリック・ギター用のエフェクターであるワウワウを接続し、凶暴なトーンを演出した。
こうして、マイルス・ディヴィスのバンドは、電気化を完了させたのである。
「ミュージシャンは、自分が生きている時代を反映する楽器を使わなきゃダメだ。」
いつの時代でも、マイルスは、周囲のものすべてを自分の中に取り込んでしまおうとしていたのだ。
60年代後半のマイルスは、もはやジャズだけでは満足できなくなっていたのである。
| |
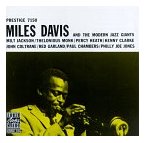 | |
↑
『マイルス・ディヴィス&ザ・モダン・ジャズ・ジャイアンツ』(1956年)
| |
『バグズ・グルーヴ』(1954年)
↓
| |
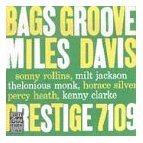 | | |
 | |
↑『ザ・コンプリート・ライブ・オブ・ザ・プラグド・ニッケル』(1965年)7枚組!
これを聴くとジャズのすべてがわかる、という圧倒的な評価をする人が多い。
| |
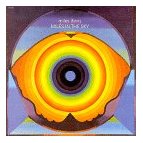 | | |
↑
『マイルス・イン・ザ・スカイ』(1968年)
| |
3、「史上最強のロックバンドを結成するんだ!」
1970年8月26日~30日の5日間。イギリス南部の港町ポーツマスからフェリーで30分ほどの距離にある小さな島、ワイト島で大規模なロック・フェスティバルが開催された。観客動員数は60万人以上といわれ、数字の上では“伝説のウッドストック”をもしのいでいる。
出演したミュージシャンは、ジミ・ヘンドリックス、ザ・フー、フリー、テン・イヤーズ・アフター、ジョニ・ミッチェル、ドアーズ、エマーソン・レイク&パーマー、ムーディ・ブルース、ジェスロ・タルといった、英米を代表するロック・ミュージシャンばかり。その中に、マイルス・ディヴィスの名前があった。
出演を発表した記者会見の席上、マイルスはこう言った。
「史上最強のロックバンドを結成するんだ!」
「…!」
マイルスは、本気でロックを征服しようとしていたのか?そんなに万物を、アンタを中心に回してみたかったのか?
またもや、マイルスに一蹴されそうである。
「So what?」
1960年代、ジャズは急激に変貌を遂げた。
音楽理論を極限まで追求したジャズは、新しい手法を生み出したのである。それが、“モード”だ。“モード”をわかりやすく解説すると、「コード・チェンジを気にせず、ひとつのスケール(音階)をよりどころとして、アドリブを展開する」ということになる。これは、複雑になり過ぎたジャズに対する、アンチテーゼといえよう。“モード”以前のジャズでは、コード・チェンジをするたびにスケールを変えるという、超人的な技術が要求されていたのだ。
前述のジョン・コルトレーンは、この“モード”を追求し続け、最終的にフリー・ジャズに到達して、この世を去った。マイルスは、そんな彼の姿に、ジャズの限界を見てしまったのである。
そしてマイルスは、「コード・チェンジを気にせず、ひとつのスケール(音階)をよりどころとして、アドリブを展開する」ことを、当たり前のように実践している音楽を見つけた。それが、ブルースをベースにして、急速な進歩を遂げていたロック・ミュージックである。当時の主流であった長時間にわたるアドリブ演奏は、まさにジャズでいう“モード”そのもの。クリームもジミ・ヘンドリックスも、無意識のうちに“モード”手法を実践していたといえるのだ。
またファンクは、低音部を主体としたひとつのテーマを延々と繰り返すことで、独特の昂揚感を生み出している。和音の一部を固定した、この“ペダル・ポイント”と呼ばれる手法もまた、“モード”に非常に近いものと考えられる。マイルスは、ブルースやファンクをロック・ミュージックと同じジャンルとみなし、これらを総称して“ロック”と呼んだのである。
マイルスは、ここに新たな可能性を見い出した。
音楽のルールは、できるだけシンプルな方がいい。そうすれば、演奏しているミュージシャンは、自己表現に集中することができる。ジャズ・ミューシャンよりはるかに音楽理論に疎いロック・ミュージシャンが、ジャズ・ミューシャンなど問題にならないほどの圧倒的なパワーで自己表現をしている姿を見て、マイルスはひそかに決心したのだ。
「史上最強のロックバンドを結成してやる!」
こうして、マイルス・ディヴィスは、チック・コリア、キース・ジャレット、ジャック・ディジョネットらをともなって、ワイト島のロック・フェスティバルに乗り込んで行ったのである。
しかし、
マイルス・ディヴィスが“ロック”に興味を持った理由は、これだけではなかったのだ。
このゴーマンなオッサンにもひとつだけ、自分の意志ではどうにもならないことがあった。
それは、“肌の色”である。
プロ・デビューしてそれほど経っていない時期に、マイルスはヨーロッパ・ツアーを経験した。そして、パリで、生まれてはじめて“自由と平等”を満喫したのである。フランスは、早くから人種差別の希薄な国であった。マイルス青年は、ここでのびのびと創作活動をし、恋をした。無上の喜びを味わう日々が続いたのである。
しかし、
フランスからアメリカに帰国した途端、マイルスは“人種差別”という現実と、ふたたび向き合わなければならなかった。これは、人一倍プライドの高いマイルスには、堪え難い現実であったに違いない。
「肌の色が、黒いだけじゃないか。」
マイルスは、お得意の「So what?」で一蹴したかったことだろう。
しかし、「So what?」では済まされなかったのだ。
失意のマイルスは、ヘロインで現実逃避を図り、やがて中毒になってしまった。
1970年前後は、黒人全体の発言力が大きくなった時代だ。この“ブラック・パワー”運動を象徴するような存在であったのが、ジェイムズ・ブラウンやスライ&ファミリー・ストーンといったファンク系のミュージシャン。そして、ジミ・ヘンドリックスであった。
ジェイムズ・ブラウンは、白人に媚びることなく、“ゴッド・ファーザー”の地位を手に入れた。ウッドストックにおけるスライ&ファミリー・ストーンは、白人黒人という人種を超越して、会場中の若者を煽動した。ジミ・ヘンドリックスは、白人を従えたバンドで活動し、カリスマ扱いをされている。黒人がリーダーになってもいい時代がやってきたのだ。
マイルスは驚き、そして共感した。
「これで、俺のコンプレックスは解消される。」
ワイト島のロック・フェスティバルから18日後の1970年9月18日、ジミ・ヘンドリックスが急死。稀代の天才ミュージシャンは、表現したいことの大半を自分の中に秘めたまま、無情にも神に召されてしまった。
一方のマイルス・ディヴィスは、加速度的に強烈なパワーで自己表現を究めて行く。自己の深層にあるカオスティックな部分(彼はこれを、“プリンセス・オブ・ダーク”と呼んでいた)を、さまざまな形態の音楽を取り込むことによって、次々と形にして行ったのだ。この時期のマイルスの活動は、“神がかり”的と表現したくなるほど、鬼気迫るものであった。
そして、
1975年2月1日。
大阪フェスティバル・ホールにおけるマイルス・ディヴィスは、ついに“到達すべき”頂点へ達してしまったのである。
この時のライブは、『アガルタ』、『パンゲア』という2枚のアルバムとして作品化されたが、この2枚こそがマイルス・ディヴィスの、いやアメリカン・ブラックミュージックの終着点であったのだ。ここには、ジャズもロックもブルースもファンクも民俗音楽も、ありとあらゆる音楽の要素が存在しているが、しかしそのどれにも分類することができない音楽が成立している。
そこには、この世でただひとつしかない、“マイルス・ディヴィス”という音楽が存在しているのである。
マイルスは、音楽で表現したいことをすべて表現し尽くした。万物はたしかに、彼を中心に回っていたのである。
ここで、彼が神のもとに召されていたら、「マイルスは神である」と言われたことであろう。しかし、マイルスは死ななかった。
“肌の色”と同様、このゴーマンなオッサンにはもうひとつだけ、自分の意志ではどうにもならないことがあった。
それは、“自分の寿命”だったのである。
| | | | |
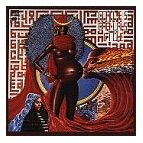 | |
↑ジャケットの雰囲気がアヤシイ。
『ライブ・イーヴル』(1970年)
| |
『マイルス・デイビス・アット・フィルモア』(1970年)
↓かなりロックっぽいが、2枚組で4曲!
| |
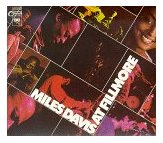 | | | |
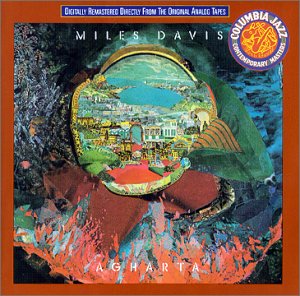 | |
↑『アガルタ』(1975年)と↓『パンゲア』(1975年)
マイルスの、というより70年代ブラック・ミュージックの終着点と言うべき作品。 | |
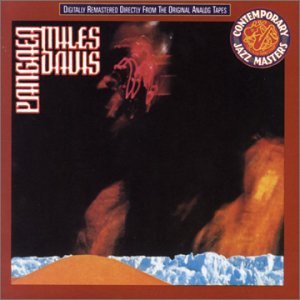 | | |
| | | 4、「弾く気にならなけりゃ、楽器に触れなければいい!」
マイルス・ディヴィスの“黄金のクィンテット”を支えたピアニスト、ハービー・ハンコックがある時期スランプに悩まされていたという。ピアノに向かっても、いいフレーズが出てこない。気分転換に、何をやってもダメだ。しまいには、ピアノを弾くことが苦痛に思えるようになってきた。
ハービーは、マイルスに相談をした。
「どうしたらいいだろう?」
マイルスは笑いながら、たった一言こう言い放ったそうだ。
「しばらく、ピアノに触れなければいいのさ。」
「…!」
ミュージシャンは、毎日楽器に触れていないと、感覚が鈍ってしまうんじゃないのかい?アンタは、それと正反対のことをハービーにススメたワケ?
またもや、マイルスに一蹴されそうである。
「So what?」
『アガルタ』、『パンゲア』で完全燃焼してしまったマイルス・ディヴィスは、それからの5年間というもの、ただの一度もトランペットに触れなかった。それでは、何か他の活動をしていたのかというと、そうでもない。文字通り、“何もしていなかった”のである。マイルスのこの5年間は、スランプに陥ったミュージシャンがよくやる“充電期間”とは、まったく異なる性質のものだったということがよくわかるだろう。しかし、彼はこのまま終わりはしなかったのだ。
マイルスは、音楽活動を休止して5年目にあたる1980年頃から、さかんに絵を描くようになった。そしてその時期に、音楽界への復帰を決意したのだ。なにか、ヒラメくものがあったに違いない。しかし、前述のように、ミュージシャンは、毎日楽器に触れていないと、感覚が鈍ってしまうものだ。とくに、トランペットのような管楽器では尚更だ。口の中が、激しいブローイングに耐えられなくなってしまうのである。
結局、マイルスはトランペットを吹くためのリハビリに、1年間を費やしてしまう。そのため、マイルスが音楽活動を休止した期間は、1975年から1981年の通算6年間ということになる。
6年の歳月は、音楽界の様相を一変させていた。かつて、マイルスが試みたジャズとロックの接近は、“フュージョン”というジャンルを形成していた。マイルスのバンドに在籍していたメンバーはみな独立し、チック・コリアはリターン・トゥ・フォーエヴァーを、ウェイン・ショーターとジョー・ザヴィヌルはウェザー・リポートを、ジョン・マクラフリンはマハビシュヌ・オーケストラを、ハービー・ハンコックやキース・ジャレットはソロになり、“フュージョン”の発展に貢献した。
しかし、マイルスが復帰した1981年頃になると、もはや“フュージョン”の基本理念は薄れ、表層的な部分のみをとらえた、“耳障りのいいBGM”になり下がっていたのである。それでもマイルスは、そんな“フュージョン”を土台にして、新たなアプローチを始めたのだ。
音楽評論家たちは、マイルスを冷笑した。
“燃えカスがくすぶっている”、“残りものをあさっている”、“帝王の末路”…、辛辣をきわめた表現がマイルスに送られた。
それでも、このゴーマンなオッサンは「So what?」を連発していたのだ。
1980年代も後半にさしかかった頃、マイルスはプリンスやキャメオといった、若いミュージシャンとさかんに交流を始めるようになった。冒頭で紹介した佐藤孝信氏と出会った頃のマイルスは、積極的に創作活動に励んでいたそうである。またもやマイルスには、新しい音楽の地平が見えていたのだろう。
1991年、マイルス・ディヴィスは新作『ドゥー・バップ』を発表。
流行のヒップ・ホップにのって、ひたすらミュート・トランペットを吹く。その、あまりの完成度の低さに、評論家たちは酷評をした。しかし、そんな完成度の低いアルバムを発表してしまうマイルスだからこそ、驚愕すべきミュージシャンといえるのである。とどまることをしらない、飽くなき前進。前へ、前へ、とにかく前へ進むことだけを繰り返すマイルスが、また新しい世界を切り開こうとしている。評論家たちには、そんなマイルスの意志が伝わらなかったのであろうか。
マイルスは、『ドゥー・バップ』の続編で、新しい世界を提示してくれるはずであった。そして、それは間違いなく、高い完成度を誇るはずであった。
しかし、
『ドゥー・バップ』の続編が発表されることはなかったのである。
1991年9月28日、マイルス・ディヴィス(本名マイルス・デューイ・デイヴィス3世)永眠。享年65歳。
やはり、“自分の寿命”だけは、どうにもならなかったのだ。
マイルス・ディヴィスは、その生涯に2度絶頂期を迎えている。
“黄金のクィンテット”、そして『アガルタ』と『パンゲア』。いずれも完璧なまでに、自己を表現し尽くしている。多くのミュージシャンがぶつかり悩む壁を、2度もクリアしている事実は驚異的なことである。そして、3度目の絶頂期を迎える寸前に、寿命が尽きた。
さぞかし、無念だったであろうと思うが、きっとマイルスは一蹴するだろう。
「So what?」
そう、万物を自分中心に回したゴーマンなオッサンには、また万物すべてが「So what?」だったのかもしれない。
| |
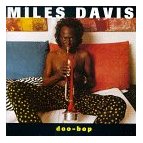 | |
↑
『ドゥー・バップ』(1991年)
| |
 | 初出:「週刊・文学メルマ」2002年8月28日号~9月25日号 | |
| | | | | | | | |