| | | | | | |
| シリーズ:歴史から抹消されたミュージシャン・第1回 | |
「Who are you?」の悲劇
リッチー・ブラックモアの後任としてディープ・パープルに加入した男、トミー・ボーリン
| |
| | |  | |
1、プロローグ
1、2年前のことだと記憶しているのだが、「♪フー、アー、フッ、フッ、フッ、フッ♪」と、ザ・フーの「フー・アー・ユー?」がテレビのコマーシャルで流れていたことがあった。「あれ?ザ・フーじゃん。うっそー、信じられなーい。」と思った人も多かったのではないだろうか。私など、「20世紀も終わりに近づいた頃になって、ザ・フーで日本中を洗脳しようなんて、少し遅すぎやしないかい?キース・ムーンがあの世で笑っているぞ。」などと思ってしまった。まあ、そうは言っても、自分の好きなミュージシャンの曲が思いがけない場面で流れてくると、おもわずニヤリとさせられることはたしかである。「このコマーシャルの選曲したヤツ、センスいーなあ…。」なんてね。
「フー・アー・ユー?」、ヒラタクいえば「オマエは誰だ?」ということだ。
1979年初夏。東京は中野サンプラザ。
スコーピオンズ2度目の来日公演のことである。
初来日時に、その凄まじい破壊力で、日本中のハードロック・ファンに脳天逆落しをくらわせ、名盤『トーキョー・テープス』を残した必殺のギタリスト、ドイツのジミヘンことウルリッヒ・ロスは、すでにスコーピオンズから脱退していた。ところが、失意のファンに対し、こんな情報が流れてきたのだ。「UFOを脱退した、マイケル・シェンカーがスコーピオンズに復帰。日本ツアーも実現!」会場中のファンが待ちのぞんでいたのは、初めて日本のファンの前に姿を現す神秘のギタリスト、マイケル・シェンカーであった。我々は、兄弟仲良くフライングVを持って並ぶ姿を、今や時遅しと待ちこがれていたのである。
会場の照明が落ち、演奏がはじまった。
「?」
メンバーが登場した瞬間、誰の目にも映った光景は、片方のギタリストが持っているギターが、エクスプローラだということだった。「さすがに、2人共フライングVでは、ルックス的によくないのでやめたのかな?」誰もが、最初はそう思ったことだろう。しかし、時間が経過するにつれて、事態が明らかになってきた。歌の文句ではないが、仕草が違う、フレーズが違う、髪型が違う、…。「あれは、マイケルじゃない!」1曲目が終わる頃には、再後列の席にいたファンも、はっきりとそう認識したことだろう。
「あれ、誰ですかねぇ?」私の周りで、そんな言葉がささやかれ始めた。
日本の観客は紳士的だから、心で思っていてもその言葉は口に出さなかった。でも、私は確信するが、この時の会場中に充満していた声なき言葉は「オマエは誰だ?」。「フー・アー・ユー?」である。
その後、すっかりバンドになじんでしまったマティアス・ヤプスは、「みんな、俺のことを歓迎してくれてるな。」と勘違いしながら、うれしそうにギターを弾いていた。しかし、スコーピオンズは、このメンバーチェンジの後、ポップなハードロック・バンドとしてワールドワイドな成功をおさめるのだ。おかげで、この話しを笑い話しとして語ることができるのだが、読者のみなさんは、この「オマエは誰だ?」がシャレにならなくなった、悲惨な一例があることを知っていますか?それが、今回の主人公である、故トミー・ボーリンのおはなし。そう、あのリッチー・ブラックモアの後任としてディープ・パープルに加入した男である。
| |
| | 2、ラストコンサート・イン・ジャパン
トミー・ボーリンに対する一般的な評価は、どのようなものだろうか?
我々の世代のロックファンの間では「ディープ・パープルをダメにしたヤツ」とか「日本公演のとき腕をいためていて、ロクにギターを弾けなかったヤツ」とか、惨澹たるものである。彼にとっての最大の不幸は、その腕をいためていた史上サイテーの日本公演が、『ラストコンサート・イン・ジャパン』というアルバムとして発表されてしまったことであろう。(それも急逝したトミーの追悼盤としてだ。)そして、私とトミーの初めての出会いは、他ならぬこの『ラストコンサート・イン・ジャパン』であった。
1977年。私が、高1の夏のことである。
悪友の1人が、笑うためにディープ・パープルの『ラストコンサート・イン・ジャパン』を買ったという。(トーゼン、30cmLPレコード)「とにかく笑えるから、みんなで聴こう。」ということになり、5・6人の仲間が放課後の視聴覚教室に集まった。
「それじゃ、いくぜ。」と、B面の「スモーク・オン・ザ・ウォーター」から「ハイウェイ・スター」を一気に流す。「ギャハハハハハ。」「こりゃー、ひでー。」こうなると、悲惨を通り越して笑いしかでてこない。これが、あの『ライブ・イン・ジャパン』を発表したグループと、同一グループなのだろうか?だいたい、ディヴィッド・カヴァーディルにイアン・ギラン時代のレパートリーを歌わせるなよ。ヴォーカルスタイルが正反対なんだから、そりゃ酷ってもんだぜ。つぎに、グレン・ヒューズのヴォーカルもなんとかしろよ。キンキン、ハイトーンでシャウトしていたかと思えば、「ンンー」゛とうなりだす。シャシャリでてきて、ディヴィーの歌をジャマすんじゃねーよ。ンっとに、もう!それよりもなによりも、このギターはナンだぁ?オレのほうがうまいぞ!コイツ、ギター弾けねーんじゃねーのお?と、まぁ非難ごーごーである。
ひとしきり笑ったところで、だれかが「ところで、A面はどうなの?」と言ったら、持ち主いわく「いやー、まだ聴いとらん。なにしろ、B面聴いて笑いこけていただけだから。」とのこと。「じゃあ、聴いてみっか。」と、レコードを裏返す。数秒後、イントロダクションが響き出す。1曲目は「紫の炎」だ。…「まぁまぁじゃん?」「うん。悪くはないね。」ギターが引っ込んでいる分、ジョン・ロードのオルガンががんばっていて、なにやらプロコル・ハルムみたいな「紫の炎」である。まぁ、許容範囲でしょう。2曲目「ラヴ・チャイルド」、3曲目「ユー・キープ・オン・ムーヴィン」。この時点では、アルバム『カム・テイスト・ザ・バンド』は未聴だったので、この2曲ははじめて聴いた。「こういう曲をやっていたんだ。」「けっこう、カッコいいじゃん?」。そして4曲目。…「うん?」、「お!」、「なにこれ?」、「いい曲じゃん?これ。」、「これ、トミー・ボーリンの曲だよ。」、「ヴォーカルもコイツなんだ?」、「はぁー」…。4曲目、そう「ワイルド・ドッグ」、トミー・ボーリンのソロアルバム『ティーザー』に収録されている曲である。
「ワイルド・ドッグ」を何度もリプレイしているうちに、4期ディープ・パープルを笑う会はいつのまにか、トミー・ボーリンをたたえる会に変わってしまったのである。
| |
 | |
| | 1975年12月、ディープ・パープルのメンバーとして来日した、トミー・ボーリン。
手にするギターは、ヤマハ・SXシリーズの試作品。
メーカーに、モニターとして協力した。
| |
| | | |  | |
3、『ティーザー』と『カム・テイスト・ザ・バンド』
「ワイルド・ドッグ」にショックトリートメントを受けた私は、同曲を収録したアルバム『ティーザー/トミー・ボーリン』を探しまくった。当時私が住んでいた、東京・足立区内のレコード屋には置いておらず、お茶の水でも見つからず、やっと新宿の某レコード店で見つけた。高1の夏休みのことである。そして、苦労の末に手に入れたアルバムの内容はすばらしいものであった。
アメリカン・バラードの王道路線といえるような「ドリーマー」、「ワイルド・ドッグ」、「ロータス」。リズム・アプローチに意欲を見せた、ボサノヴァ調の「サバンナ・ウーマン」、レゲエ調の「ピープル、ピープル」。鋭角的でエネルギッシュなジャズ・ロック調のインスト、「ホームワード・ストラット」、「マーチング・パウダー」。(この曲などは、ジェフ・ベック師匠の『ワイアード』にはいっていてもおかしくないような曲である。それもそのはず、ヤン・ハマー(Syn)、ナラダ・マイケル・ウォルデン(Ds)なのだ!)そして、ストレートなR&Rタイプの「グラインド」、「ティーザー」。(この曲は、モトリー・クルーがカヴァーをしているので、ご存じの方も多いのでは?)
各曲がヴァラエティに富んでいながら、聴き手に散漫な印象を与えないよう、みごとに計算しつくされた構成と演奏。そこでは、『ラストコンサート・イン・ジャパン』のトミーとはまったく別人の、有能なソングライターでありギタリストである1人のミュージシャンが、惜しげもなく自己の才能を誇示していたのである。私はすっかり、トミーにハマってしまった。
つぎに私がGETしたのは、(再結成前の)ディープ・パープルのラスト・アルバム『カム・テイスト・ザ・バンド』である。食わずぎらいだった4期ディープ・パープルは、私に2度目のショックを与えてくれた。これは、カッコいいロック・アルバムである。ジョン・ロードが、ディープ・パープル時代のベスト3にあげているのもうなずける内容だ。リッチー在籍時のラスト・アルバム『嵐の使者』で見せていた、中途半端なアメリカン・ファンク路線が徹底されていて、実に気持ちがいい。
「ゲッティン・タイター」のイントロで聴かせる16ビートのコード・カッティングなどは、間違ってもリッチーにはできない(という以前にやらないか?)ような芸当である。そんなプレイを、トミーはさりげなくキメてしまう。そして、ディヴィッドもグレンも、トミーの加入によってイキイキとしている。このアルバムは、ファンキー・ハードロックの元祖といえる、歴史的な意味を持った作品である。ここまできて私は、トーゼンあたるべき疑問にブチあたった。
「なぜ、トミーはディープ・パープルに参加したのだろうか?」そして、「なぜ、トミーはここまで酷評されているのだろうか?」
| |
ディープ・パープルのメンバーの中では、もっともトミーを理解してくれた、盟友グレン・ヒューズ(b)とのショット。
| |
| | 4、悲しきアメリカン・ドリーム
ここで、トミーの一生を簡単に追ってみたいと思う。
1951年8月1日 アメリカ・アイオワ州で生まれる。
1968年(17歳) 高校をドロップ・アウトし、コロラド州デンバーに移る。
※この頃、デンバーの空港で警察に補導されたことがあるらしい。どうも、ヤク関係のにおいがするが、本人は否定している。
1970年(19歳) “ゼファー”というローカル・バンドに参加。71年に脱退するまでに、2枚のアルバムを発表している。
1973 年(22歳) 8月頃、ジョー・ウォルシュの後任として、アメリカン・ハードロック・バンドの雄“ジェイムズ・ギャング”に参加。74年の解散までに、『バン』(73年)・『マイアミ』(74年)2枚のアルバムを発表。またこの時期、バンド活動と並行してセッション・ワークも積極的にこなしており、元マハヴィシュヌ・オーケストラのドラマー、ビリー・コブハムの『スペクトラム』(73年)・元ウェザー・リポートのドラマー、アルフォンソ・ムゾーンの『マインド・トランスプラント』(74年)はその代表作である。
1974年(23歳) “ジェイムズ・ギャング”の解散と同時に、初のソロ・アル バム『ティーザー』の制作にはいる。(7月頃~)
1975年 5月 “ディープ・パープル”に参加。
同年10月 “ディープ・パープル”、『カム・テイスト・ザ・バンド』を発表。
同年11月 ソロ・アルバム『ティーザー』発表。
同年12月 “ディープ・パープル”来日。
※12月15日の日本武道館におけるライブが、のちに『ラスト・コンサート・イン・ジャパン』としてレコード化される。
1976年 7月 “ディープ・パープル”解散。
同年11月 2枚目のソロ・アルバム『プライヴェート・アイズ』を発表。
同年12月4日 ジェフ・ベックのマイアミ公演をサポート後、ヘロイン中毒のためホテルで死亡。 (享年25歳)
トミーがディープ・パープル加入時に交わした契約条件というのが、ようやく最近になってわかってきた。その中に、次のような一項があってたいへん驚いた。それは、「バンドのメンバーとしてレコーディングやコンサートを行ないながらも、オフにはソロプロジェクトに携って構わない。」という個所である。なんと、トミーは最初から、ディープ・パープルとソロ活動を並行させるつもりであったのだ!
ここで注目すべき点は、前述の年表でも確認できることだが、ソロ・アルバム『ティーザー』が発表されたのが、ディープ・パープル加入後であるということだ。ジェイムズ・ギャング脱退直後から制作されていたにもかかわらず、ディープ・パープルのニュー・アルバム『カム・テイスト・ザ・バンド』よりも後に発表されている。どういうことなのだろうか?
ここで私の推測だが、トミーは待望のソロ・アルバムを作り始めてはみたものの、資金繰りに困り作業が進まなくなっていたのではないだろうか?そんな時に、ディープ・パープルほどの大物グループから声をかけられれば、誰だって最高のパトロンが現れたと大喜びするでしょう?少々目指す音楽の方向性が違っていたとしても、この際気にするほどのことでもない。それよりも、莫大な契約金とネーム・バリュー。富と名声を一気に手に入れ、サクセス・ストーリーをも手にする。アメリカ人なら当然、そういう発想をするでしょう。そう考えると逆説的だが、『ティーザー』は、“ディープ・パープル”なくしては陽の目を見なかったかもしれない作品ともいえるのだ。念願のソロ・アルバムに満足し、英国の老舗大物バンドに新風を吹き込み、トミーは意気揚々としていたことだろう。
しかし、世の中そんなに甘くはなかった。
| | |
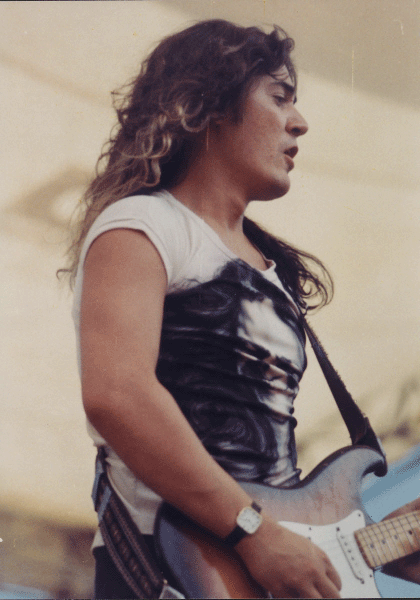 | |
デンバーのトミー・ボーリン。
コロラド州デンバーは、彼のホームタウンである。
ファンは、いつでもトミーをあたたかく迎えてくれた。
phote by David Polhemus & John Hunter
| | |
5、「Who are you?」
ディープ・パープルのステージに立ったトミーには、観客からモーレツな「オマエは誰だ?」の大合唱が襲いかかる。「ま、新参者ってヤツは、はじめはこんなもんさ。」と余裕をカマシていられていたのも最初のうちだけ。トミーに対する「オマエは誰だ?」コールは、どんどんエスカレートしてゆく。向こう(欧米)の観衆は、冒頭で例に上げた、日本の観衆のように紳士的ではないのだ。
さらに、「オマエは誰だ?」はしだいに「リッチーはどうした。」と前任者を求める声に変わり、果ては「リッチーをだせ!」コールへと変わってゆく。これはキツイ。この、ファンのリッチー・コールについにキレたトミー君が、しまいにはリッチーの住所と電話番号を書いた紙を客席に向かってバラまいたというのだから、そのすさまじさは想像を絶するレベルだったのだろう。さらに悪いことには、ひどいヘロイン中毒だったトミーが、ヤクの影響で好不調のはげしいステージを見せるようになる。これが、ファンには悪い印象にうつり、トミーに対するブーイングはますますひどいものになってゆくのである。(来日公演のとき、左腕が使えず満足なプレイができなかったのは、悪質なヘロインを打ったことによるものだと知った時はビックリした。何が、寝違えただぁ!)
ディープ・パープルというバンドのサウンドは、保守的な様式美の権化といわれがちだが、これはあながちメンバーの責任だけではないようだ。バンドがサウンドに変革を求めたアルバムは、ことごとくファンにソッポをむかれるのだ。2期の『紫の肖像』、3期の『嵐の使者』。いやそれどころか、脱退後の各メンバーの活動に対しても同様である。それゆえに、レインボーもホワイトスネイクも、3期ディープ・パープル・サウンドの焼き直しに終始しているわけだし、ファンキー・クロスオーヴァーサウンドを目指したイアン・ギランも軌道修正を余儀なくさせられたのだ。(今の、リッチーのツッパリもいつまでつづくものやら。)スティーヴ・モーズが加入した現在ですら、「♪スモ~ク・オン・ザ・ウォ~タ~♪」なのである。大英帝国の老舗の登録商標は、若きアメリカ青年の夢と才能で塗りかえられるほど、ヤワなものではなかったのだ。
さらに、狂った運命の歯車が、トミーに追い討ちをかける。ディープ・パープル解散後、再起をはかるヒマもなくこの世を去ってしまった彼のために、追悼盤と称して例の史上サイテーの『ラストコンサート・イン・ジャパン』が公式発表されてしまったのである。私は断言するが、もしトミーが生きていたら、どんな事情があるにせよ、自分の力量を半分も発揮できなかったこのアルバムの発表に対して、絶対OKは出さなかったはずである。結局、トミーに与えられたものは、本人には二度と挽回する機会がなくなった“汚名”だけなのだ。「ディープ・パープルをダメにしたヤツ」、「日本公演のとき、ロクにギターを弾けなかったヤツ」…。本人の能力や意志とはまったく無関係な力の作用によって、ここまで評価を落としているミュージシャンの例は、これまでのロックの歴史の中で他に類を見ない。あまりといえば、あまりにもかわいそうなトミー君である。そう思いません?
| | | |
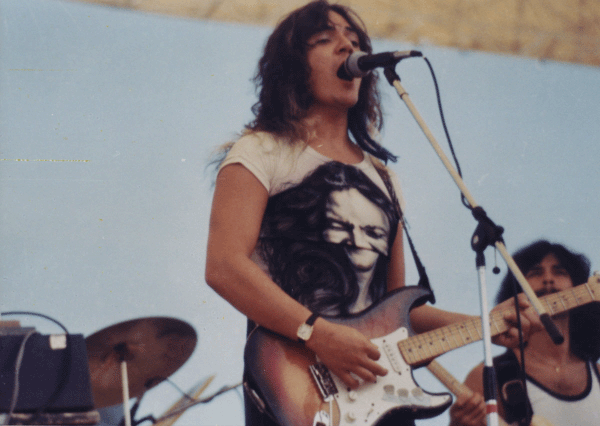 | |
ベーシストから判断すると、このショットは、ディープ・パープル解散直前に行われた、1976年夏のソロ・ツアー時のものと思われる。
この数カ月後に、トミーはこの世を去っている。
phote by David Polhemus & John Hunter
| |
| | | | 6、エピローグ
1996年以降、“トミー・ボーリン・アーチヴス”なる(遺族が経営していると思われる)機関が、彼の未発表音源を中心とした作品のリリースを、積極的に行っている。また、ミュージシャンであった彼の実弟とグレン・ヒューズを中心とした、トリビュート盤も発表された。どうやら、本国アメリカでは、すでにトミーの再評価が始まっているようだ。あなたも、日本における、トミー・ボーリンの再評価運動に参加してみませんか?ディープ・パープルの人気が異常に高い日本だからこそ、彼の再評価には大きな意義があるのではないでしょうか。
私は、多感な青春時代に感銘を受けたミュージシャンが、いまだに汚名にまみれたまま、時代の彼方に忘れ去られていることが残念でたまらない。その高い音楽性は、今だに輝きを失っていないのだから。とにかく、ひとりでも多くの人が彼の作品に触れて、その素晴らしさを少しでも後世へ伝えてくれれば、いつの日かその汚名も薄らいでゆくことだろう。われわれが後世に伝えるべきことは、汚名や悪評ではなく、素晴らしさや輝きであるべきだと思う。また、そうすることが、ポジィティブな、ロックへの接し方のあるべき姿だと、私は信じている。
歴史から抹消されようとしているミュージシャンに、もう一度スポットライトを当ててみよう!
| | | |
 | |
7、私のおすすめベスト3
『ティーザー/トミー・ボーリン』
まずは、黙ってコレを聴いてくれ!(別のコーナーのタイトルではない!笑)この作品が、アメリカン・ロックの名作にランクインされないことが、今世紀最大の不幸なのだ。私は20年来のおツキアイになるけど、いまだに年に数回は耳にしている。チャーこと竹中尚人氏が、「ソロアルバムの一作目ってヤツは、そいつのそれまでの人生すべての凝縮になるから、その後それを越えるものはなかなかできないワケよ。」と語っていたことがあるが、この作品を聴くにつけ、まさにその通りだと実感してしまう。ここには、トミーの人生すべてが詰まっているといっても過言ではあるまい。逆に、コレを聴いて何も感じないひとは、これ以上トミーの世界には入れないと思うよ。
参加メンバーもソーソーたる面々で、ディヴィッド・フォスター(Key)、ディヴィッド・サンボーン(Sax)をはじめ、後にTOTOに参加する名セッションマン、ジェフ・ポーカロ(Ds)(この人も故人なんだよなー)、『ピーター・フランプトン・カムズ・アライブ』に参加したスタンリー・シェルドン(B)、なんとヤン・ハマー(Syn)、とどめにナラダ・マイケル・ウォルデン(Ds)(一曲のみ)、もひとつオマケにジェネシスのフィル・コリンズ(Per)(一曲のみ)ときたもんだ。このメンツを前にして、堂々たる自己の世界を展開しているトミーはやっぱりスゴイぞ!
とにかく、まずコレを聴くべし!
『カム・ティスト・ザ・バンド/ディープ・パープル』
この作品を、“ディープ・パープルのアルバム”として聴いてはいけない!“ディー
プ・パープルという名前のロックバンド”のアルバムとして聴くべきである!先入観や固定観念なしで聴いてみれば、最高に良質の作品であることがよくわかるだろう。とにかく4期ディープ・パープルを、マジメに評価してあげようよ!この作品は、もっと評価されるべき名盤なんだから!そして、その名盤づくりに多大な貢献を果たしたトミーの力量を、もっと認識すべきだよ。
『スペクトラム/ビリー・コブハム』
この作品が、1973年に発表されているという事実に注目してほしい。ジェフ・ベックの『ワイアード』に先がけること3年、ヤン・ハマーはすでにここでそのサウンドの予習をしているのだ。(この作品を聴くと、『ワイアード』がヤン・ハマーの手によるものだということが確認できる。)このサウンドは、ハイパーテクノハードジャズロック(なんのこっちゃ)とでもいえばよいのかしらん。3年早すぎた音だね。おかげで、当時は一部のミュージシャンの間で話題になったくらいで、大多数のひとはその革新性にピンとこなかったみたい。(ちなみに、このアルバムを聴いたディヴィッド・カヴァーディルが、トミーをパープルに推薦したらしい。)このアルバムでトミーは、ヤン・ハマーに煽られながら、暴走ぎみにキレまくったフレーズを連発していて、まさにアクレッシヴの一言。
ギタリストとしてのトミーを聴くには、ベスト・ワン!
※番外編『ライブ・アット・エベッツフィールド 1976・5・13』
これは、例のトミー・ボーリン・アーチヴスから1996年に発表された、未発表音源。ディープ・パープルの76年全米ツアー終了時のオフを利用して行われた、ソロ・コンサートを収録したものである。『ティーザー』からの曲を中心として、リラックスした演奏を聴かせてくれるが、目玉はなんといってもナマのナラダ・マイケル・ウォルデンが聴ける貴重な(というより唯一の?)ライブであるということ。そのうえ、ナラダのソロ・アルバムから「ディライトフル」を演奏(トーゼン、ヴォーカルも彼。そういえば、ナラダのファースト・ソロアルバムもいつになったらCD化されるのかしらん?)しているので、それだけでも一聴の価値はある。演奏・音質も、この種のものとしては上の部類にはいるだろう。他に、元ヴァニラ・ファッジのマーク・スタイン(Key)等が参加。 | | | |
 | |
トミーが好んで使用したギターは、フェンダー・ストラトキャスター。
とくに、1950年代のモデルがお気に入りだったようだ。
この時期のストラト、実はセンターPUがいちばんイイ音なのだ。
このショットでも、PUセレクター・スィッチがしっかり、真ん中にはいっていることが確認できる。
phote by David Polhemus & John Hunter | |
 | 画像提供:Scott McIntosh | | |
| | | | | | | | | | | | | | |