| | | | | | | |
“神”と呼ばれることを、拒否した男
| |
1、エリック・クラプトンと私
「歌謡ショーみたいじゃん。」
エリック・クラプトンのステージを初めて見た私は、思わずこうつぶやいていた。
計算し尽くされたステージ進行。
シブい声と流麗なギター・プレイ。
ステージ中央で堂々と仁王立ちをするクラプトンの姿は、私に北島三郎や村田秀雄の姿を連想させた。
1980年代初頭のことである。
「たしかに、ギターはうまい。」
さきほど“流麗”と表現したが、次から次へとあふれ出てくるフレーズの数々は、見事としか言いようがない。さすが、1960年代後半に、“GOD”と呼ばれていた男だ。ハイテク・ベーシスト、スタンリー・クラークのスピードに、青息吐息でヒーコラついてきていたジェフ・ベックとは、エライ違いだ。
私がロックを聴き始めた1970年代中期に、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジは、3大ギタリストと呼ばれていた。私の好きな順では、1にジェフ・ベック、2にジミー・ペイジ、そして3ではなく、ずっと下がってエリック・クラプトンであった。神がかり的なジェフ・ベック、究極のバンド・スタイルをきわめたジミー・ペイジと比較して、エリック・クラプトンは、私に今一歩アピールしてこなかったのだ。私には、彼のギター・プレイがあまりにも整然とし過ぎていることが、かえって不満だったのかもしれない。むしろ、スリリングで先が読めない、“ちびっ子ギャング”のようなジェフ・ベックのプレイの方に、よりロックっぽさを感じていたようだ。
それでは、なぜ私は、クラプトンのステージを見に来たのだろうか。
それは、当時私と交際していた女性が、熱狂的なクラプトン・ファンだったからだ。私は、彼女との仲を円滑に保つために、ここに来たに過ぎない。クラプトンの代表作は、ほとんど耳にしていた。しかし私が彼をギタリストとして評価したのは、ブルース・ブレイカーズ~クリーム初期のみだった。その後のアルバムは、BGM程度のものとしか思っていなかったのである。
私は、一生クラプトンを自分の中に取り込めないと確信していた。
そして、私の10代が終わり、20代が過ぎ、今や30代も過ぎようとしている。
私は、30代最後の今年、1枚のアルバムと出会ったことによって、エリック・クラプトンを理解できるようになった。
いままで敬遠していた人と、ひょんなことで仲良くなったようなものである。
そのアルバムは、デラニー&ボニーの『モーテル・ショット』。
私は、初めてこのアルバムを聴いた時に、こう思った。
「やっぱり、アメリカ人にはかなわないな。」
エリック・クラプトンも、デラニー&ボニーと初めて出会った時に、やはりこう思ったはずだ。
「やっぱり、アメリカ人にはかなわないな。」、と。
| | |
| | | | 2、デラニー&ボニー
デラニー&ボニーは、1960年代後半に活動をはじめた、夫婦ヴォーカル・デュオ。デラニー・ブラムレットが夫で、ボニー・ブラムレットが妻である。彼等は、フォークやカントリーの要素を巧みに取り入れながら、ゴスペル、ソウル、ブルースといったアメリカ南部のルーツ・ミュージックに深く根ざした、独自のサウンドを展開していた。彼等のサウンドは、“アメリカ”そのものである。そして、それはどちらかというと、一般の音楽ファンではなくミュージシャンから支持を受ける、“ミュージシャンズ・ミュージシャン”的な要素が強かったようだ。
彼等は、レコード・デビュー以前から、LAあたりではかなり話題になっていたらしい。そして、ジョージ・ハリスンがわざわざ現地へ飛んで彼等の演奏テープを入手する。ジョージはデラニー&ボニーから強い感銘を受け、アップル・レコードからレコード・デビューさせることを考えていたようだ。(結局、実現はしなかった。)
諸説があるが、どうやらエリック・クラプトンにデラニー&ボニーの存在を教えたのは、このジョージ・ハリスンらしい。そして、ジョージ同様、デラニー&ボニーから強い感銘を受けたクラプトンはさっそく、当時在籍していたブラインド・フェイスの全英ツアーのサポートとして、彼等を起用する。その後、ブラインド・フェイスは全米ツアー終了後の1969年8月に、解散宣言もなく活動を停止。クラプトンはそのままアメリカにとどまり、デラニー&ボニーのバック・バンド、フレンズに参加してしまう。この時期のクラプトンの音は、『デラニー&ボニー&フレンズ・オン・ツアー・ウィズ・エリック・クラプトン』で聴くことができる。
デラニー&ボニーは、はじめての全英ツアーの時に、エリック・クラプトン宅に宿泊していた。我が物顔で振る舞うこの夫婦に、下僕のように仕えるクラプトンの姿が、皮肉たっぷりに報道されたのはこの時だ。報道は、すでにスーパー・ギタリストだったクラプトンに同情的で、「デラニー&ボニーとは、何様だ?」といった内容のものだった。しかし私は、この報道から、クラプトンがいかに彼等を畏敬していたかがうかがえると思う。クラプトンにとっては、知名度の高さではなく、ミュージシャンとして優れているかどうか、の方が重要だったのだろう。彼は素直に、自分の尊敬するミュージシャンを、精一杯もてなしただけなのだ。
『モーテル・ショット』は、デラニー&ボニーが1971年に発表したアルバムである。
もともと“モーテル・ショット”とは、ツアー中のミュージシャンが、滞在先のモーテルで行うセッションを指している。ドラム・キットを組むこともせず、電気楽器やPAを使うこともせず、生ピアノやアコースティック・ギターを中心に、タンバリンやそこいらにある箱などを叩きながら、歌を歌う。それは、ミュージシャンがもっともリラックスして、音楽を楽しんでいる瞬間といえるのではないだろうか。デラニー&ボニーはあえて、これをレコードにしたのである。
この作品のスゴさは、単なる企画モノではなく、これが作品として立派に成立していることだ。
機材を満足に使えない状態でも、彼等は見事に“アメリカ”を表現している。そこには、イギリスのミュージシャンたちが探究してやまない、ゴスペル、ソウル、ブルースといったアメリカ南部のルーツ・ミュージックが、ギッシリと詰め込まれているのだ。
これを、リラックスした状態で、気楽に演奏していることが、彼等のおそるべきところである。私が、「やっぱり、アメリカ人にはかなわないな。」と痛感したのは、ここのところだ。もう、体に染み込んでいる音が、自然に出てきているだけなのである。しかし、音楽自体のレベルは、おそるべきほど高い。それは、我々日本人には逆立ちしても、マネのできない芸当である。なぜなら、もともと我が国の土壌に、この種の音楽が存在していないのだから。
私は、『モーテル・ショット』を聴いて、このことを痛感した。
そして、私はあることに気がついたのだ。
これはイギリスでも、根本的にはまったく同じことがいえるのではないだろうか?。ゴスペル、ソウル、ブルースは、イギリスにおいても輸入文化である。
アマチュア時代から一貫してブルースを追求してきた、エリック・クラプトン。
しかし、デラニー&ボニーの音楽性の中で、ブルースはヴァリエーションのひとつに過ぎない。ゴスペルやソウルといった、他のアメリカ南部のルーツ・ミュージックと、同列の中のひとつに過ぎないのだ。クラプトンはデラニー&ボニーと出会って、この事実を思い知らされたはずである。そして、彼等の中に確実に存在している“アメリカ”の巨大さに圧倒されたのである。
この瞬間、私には1970年代のエリック・クラプトンの軌跡がすべて理解できた。
そして、彼の心理が手に取るようによくわかってきたと同時に、彼のスゴさがわかってきた。
クラプトンは、「やっぱり、アメリカ人にはかなわないな。」と圧倒された後に、こう決心したはずである。
「アメリカを、自分の中に取り込んでやる!」
そして、それを実現させてしまったことが、エリック・クラプトンの才能の非凡さを物語っているのだ。
| |
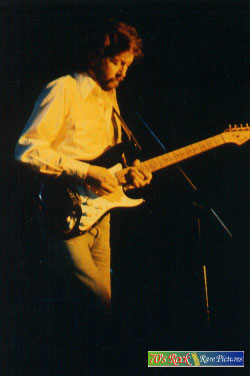 | |
| ↑1978年~79年のイギリス・ツアーにおいて | |
| ↓まるで、『スローハンド』のジャケット | | |
 | |
| | 3、70年代のエリック・クラプトン
エリック・クラプトン初のソロ・アルバム『エリック・クラプトン』は、デラニー&ボニーの全面的なバック・アップのもと1970年に発表された。クラプトンは、全世界の音楽ファンに対して、自己の方向性を明確に提示したのだ。その後、デラニー&ボニーのバック・バンドから、ジム・ゴードン(Ds)、カール・レイドル(B)、ボビー・ウイットロック(Key)の3人を引き抜き、デレク&ドミノスを結成する。そして彼等は、デュアン・オールマンの協力を得て、『レイラ』を発表するのだ。
『レイラ』
『レイラ』は、エリック・クラプトンの代表作だ。パティ(当時のジョージ・ハリスン夫人)との劇的な恋の物語は、いつまでもファンを魅了し続けている。しかし、このアルバムの名義は、エリック・クラプトンではなくデレク&ドミノスである。音作りの中心になったのは、デュアン・オールマンであったといわれている。
この時期のクラプトンは、“アメリカ”を自分の中に取り込み始めたばかりだ。すべてを、自分の独力で成し遂げるだけの自信が、まだ確立されていなかったのだろう。そこで、理想の音作りを、信頼できるミュージシャンたちに任せたのだ。クラプトンは彼等の作った音に収まり、ギターとヴォーカルを担当したに過ぎない。あくまでも、バンドのメンバーの1人に徹しているのだ。タイトル曲「レイラ」のソロ・パートが、デュアン・オールマンによるスライドギターとボビー・ウイットロックによるピアノであることは、この事実を如実に証明している。
そう考えると、 デュアン・オールマンを失ったエリック・クラプトンのショックの大きさを、容易に計り知ることができるだろう。
1971年10月29日、デュアン・オールマンはオートバイの事故により、25歳の若さであっけなくこの世を去ってしまう。前年のジミ・ヘンドリックスの死、父親代わりだった祖父ジャック・クラップの死に続く、デュアンの死。ショックのあまりノイローゼに陥ったクラプトンは、音楽界からの引退を決意。復帰までに、実に3年近くの歳月を要することになる。
この隠棲の期間は、クラプトン・ファンにあまりいい印象を与えていないようだ。しかし私は、それほど悪い印象を持っていない。逆に、この隠棲生活がきっかけとなって、エリック・クラプトンは“アメリカ”を自分の中に取り込んだのではないかと考えている。彼は、ただ休んでいたわけではない。次のステップに備えるべく、充電の期間を送っていたのだ。そして、過酷な現実と向かい合うことによって、“アメリカ”は確実にクラプトンの中に存在し始めた。
デュアン・オールマンは死して、エリック・クラプトンの中に生を宿したのだ。
『461オーシャン・ブールヴァード』~『安息の日々』
復活したエリック・クラプトンは1974年、『461オーシャン・ブールヴァード』を発表する。私は、このアルバムこそが、クラプトンの第1歩であったと評価している。
自身のバック・バンドを率いたクラプトンの姿からは、これ以前の迷いが微塵も感じられないのだ。
このアルバムを特徴付けているのは、大ヒットした「アイ・ショット・ザ・シェリフ」に代表される、レゲエの本格的な導入である。まだ、キース・リチャーズなど一部のミュージシャンが注目していたに過ぎないジャマイカのリズムを、いち早く取り入れたクラプトンの先見性はいかがなものだろう。
私は、このクラプトンのレゲエは、ファンクの代用品であったと考えている。レゲエのリズムは本来、一拍一拍が大地に捧げるように刻まれて行く。軽やかに、ハネるリズムではないのだ。極端な表現をすれば、一拍ごとに完結するリズムだ。ところが、クラプトンの「アイ・ショット・ザ・シェリフ」は、見事にリズムがハネている。ボブ・マーリィの原曲とは、明らかにリズムの解釈が違っているのだ。なぜ、彼はこのような解釈をしたのだろうか。
アメリカ南部特有の、ハネるリズム感覚。70年代中期に、ファンク・ミュージックとして一大ムーブメントを巻き起こすこのリズム感覚は、ゴスペル、ソウル、ブルースの根底に存在している。
クラプトンは“アメリカ”を自分の中に取り込む過程で、レゲエに出会った。彼はこの、まだあまり世間に知られていないリズムを身に付けることで、自分なりにファンクを消化できると確信したのだろう。ファンクをそのまま取り込まなかった姿勢に、英国人特有のプライドの高さが感じられる。
『461オーシャン・ブールヴァード』のサウンドは、そのまま1975年発表の『安息の日々』に受け継がれている。
『安息の日々』は比較的地味な作品であるが、各収録曲は味わい深く、クラプトンの中で“アメリカ”が確実に深化していることを実感することができる。
『ノー・リーズン・トゥ・クライ』~『スローハンド』
息抜きのように、思い切りハード・ドライビングなブルース・ギターをキメたライブ盤、『E・C・ワズ・ヒア』をはさんで、1976年に発表されたのが、『ノー・リーズン・トゥ・クライ』である。
クラプトンは、このアルバムで、ついにアコガレのザ・バンドのメンバーと、共演を果たしている。
実はクリーム在籍時から、クラプトンが理想としていたのが、このザ・バンドである。この時の共演はクラプトンにとって、自身を試す絶好の機会であったと思われる。
『レイラ』の時と同様、基本的な音作りは、ザ・バンドに任せている。しかし、『レイラ』との決定的な違いは、クラプトンがバンドのメンバーの1人として、収まらなくなっているということだ。もはや、誰と共演しても、クラプトン印の音が出るようになっている。これは、彼のヴォーカルが格段の進歩を遂げたことによるものと言われているが、もちろんそれだけではない。精神面でも大きく成長したのであろう。
『レイラ』から6年、ついにエリック・クラプトンは、“アメリカ”を自分の中に取り込むことに、確実な手ごたえを感じるに至ったのだ。
そしてクラプトンは、1976年11月26日、ザ・バンドの解散コンサートである、『ラスト・ワルツ』に参加。アコガレのバンドの最期に、立ち会っているのだ。
ザ・バンドも解散して、エリック・クラプトンの中に生を宿した。
このようなエリック・クラプトンの、一連の活動を集大成させたアルバムが、1977年に発表された『スローハンド』である。収録曲はどれもが、珠玉の名曲揃い。そして、大半の曲が、これ以後のライブにおける定番になった。どの曲にも、しっかりと“アメリカ”が感じられる。その“アメリカ”は、クラプトンが自分の血や肉の一部として、消化し切ったものである。
ついに彼は、自身の目標とする地点に到達したのだ。
『スローハンド』はセールス面でも、大きな成功をおさめた。アルバムは全米チャート初登場で2位を記録し、シングルカットされた「レイ・ダウン・サリー」は3位を記録。そして、「レイ・ダウン・サリー」は、クラプトンにとって初ヒットとなった「アイ・ショット・ザ・シェリフ」を上回るロング・セラーになった。
ここに至って、エリック・クラプトンは名実ともに、世界最高のミュージシャンのひとりになったのだ。
| | | |
↓ヘッドにタバコをさしこんで
(1980年5月15日、イギリス、ハマースミス・オデオンにおいて) | |
 | | |
| | 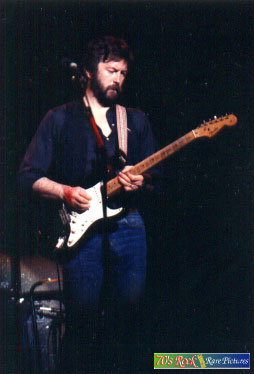 | |
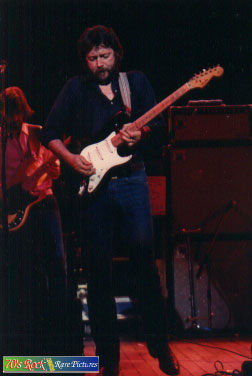 | |
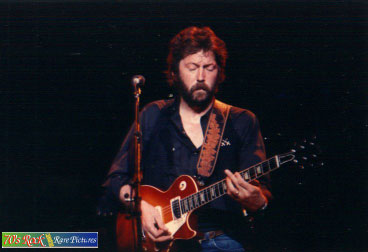 | |
↑レスポールを弾く
(1980年5月15日、イギリス、ハマースミス・オデオンにおいて) | |
| | 4、“レイド・バック”?
『スローハンド』で確立されたエリック・クラプトン・サウンドは、その後円熟の境地へ達して行った。一度円熟の境地に達するや、自身の人生が投影された私小説的な曲であっても、すべてが全世界で熱狂的に受け入れられるようになった。
冒頭で述べたように、1980年代のエリック・クラプトンのステージに接した私が、「歌謡ショーみたいじゃん。」と感じたことについては、あながち的外れとはいえまい。もう、その年代に入ると、彼のステージは、“完成されたひとつの芸”として成立していたのだ。
エリック・クラプトンが円熟の境地へと達するに至った軌跡は、求道者が人生の真理を明らかにして悟りの境地に達する過程と、非常によく似ている。不惑の年を目前に控えた私が、自身の人生について思索に及ぶ時、なぜか70年代のクラプトンの姿がシンクロするのだ。
「何を目標に、これからの人生を歩むべきか。」
「どのような方法で、自己を成熟させて行くか。」
残念ながら今の私には、まだ明確な答えが出せない。しかし、答えを出す努力だけは、絶やさないつもりだ。
クラプトンは、“神”と呼ばれることを拒否し、人生の真理を追求する苦難の道を選んだ。
世間では、そんな70年代のエリック・クラプトンに、なんの躊躇もなく“レイド・バック”という表現を使用する。しかし、これは適切な表現といえるだろうか。“レイド・バック”という表現は、表層的な音のイメージから当てられた単語である。それは、クラプトンの精神的な昂揚や気力の充実を、まったく無視していると言っても過言ではあるまい。彼自身は、少しも“レイド・バック”などしていないのだ。
私は、70年代のエリック・クラプトンに対して、“レイド・バック”という表現は使いたくない。
人生を、音楽に投影して思索することは、音楽ファンのみに与えられた特権だ。私は、これからも機会あるたびに、この特権を行使して行くことだろう。そして、今までまったく興味のなかったミュージシャンと、ある日突然接点を持つことになるかもしれない。
こうして私は、ロックの真理を追求することによって、人生を充実させていくのだろう。
| | |
 | 画像提供: |  | | |
| | | | | | | | | | | | | | |